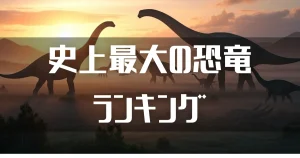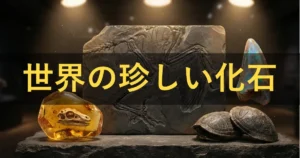子どもの頃、「恐竜はアメリカやモンゴルのもの」と思っていた人は多いでしょう。
しかし――僕たちが暮らすこの日本列島にも、確かに恐竜は生きていたのです。
1億年前。
まだ日本がユーラシア大陸の一部だった時代、福井の湿地を草食竜がのし歩き、北海道の海辺には“海のそばに暮らす恐竜”が姿を現していました。
そして近年、その証拠となる化石が、次々と日本各地の地層から発見されています。
日本で見つかった恐竜の数は、いまや10種類を超え、その多くが新種として世界に認められた存在です。
福井県・北海道・兵庫県――これらの地は、いまや“恐竜王国ニッポン”と呼ばれるほど。
この記事では、「日本で発見された恐竜化石の一覧」をはじめ、各恐竜の特徴、発見地の背景、そして今後見つかるかもしれない未知の恐竜たちまで、最新の研究成果をもとにわかりやすく解説します。
1億年前の鼓動を、いま、現代の言葉で掘り起こしていきましょう。
日本で発見された恐竜化石一覧
ここでは、これまでに日本で正式に学名が記載された恐竜14種類ををすべて紹介します。
重複種を除き、最初に発見された地点・学名を基準に発見年順で整理しています。
一覧を見ると、福井・兵庫・北海道など、全国各地で恐竜が発見されていることがわかります。
| 恐竜の名前 | 学名 | 発見地(都道府県・地層) | 記載年 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| ニッポノサウルス | Nipponosaurus sachalinensis | 樺太(旧日本領)/ヨエゾ群 | 1936 | ハドロサウルス類(草食) |
| ワキノサウルス | Wakinosaurus satoi | 福岡県/仙石層 | 1992 | 獣脚類(肉食) |
| フクイラプトル | Fukuiraptor kitadaniensis | 福井県勝山市/キタダニ層 | 2000 | 獣脚類(中型肉食) |
| フクイサウルス | Fukuisaurus tetoriensis | 福井県勝山市/キタダニ層 | 2003 | 鳥脚類(草食) |
| アルバロフォサウルス | Albalophosaurus yamaguchiorum | 石川県白山市/クワジマ層 | 2009 | 鳥盤類(初期草食) |
| フクイティタン | Fukuititan nipponensis | 福井県勝山市/キタダニ層 | 2010 | 竜脚類(大型草食) |
| タンバティタニス | Tambatitanis amicitiae | 兵庫県篠山市/佐曽利層(ササヤマ群) | 2014 | 竜脚類(大型草食) |
| コウシサウルス | Koshisaurus katsuyama | 福井県勝山市/キタダニ層 | 2015 | 鳥脚類(小型草食) |
| フクイヴェナトル | Fukuivenator paradoxus | 福井県勝山市/キタダニ層 | 2016 | 獣脚類(雑食・鳥類に近縁) |
| カムイサウルス | Kamuysaurus japonicus | 北海道むかわ町/ヨエゾ群・ハコブチ層 | 2019 | ハドロサウルス類(カモノハシ竜) |
| ヤマトサウルス | Yamatosaurus izanagii | 兵庫県淡路島/キタアマ層 | 2021 | ハドロサウルス類(原始的草食) |
| パラリテリジノサウルス | Paralitherizinosaurus japonicus | 北海道三笠市/オソウシナイ層 | 2022 | テリジノサウルス類(草食/長い前肢) |
| ティラノミムス | Tyrannomimus fukuiensis | 福井県勝山市/キタダニ層 | 2023 | 獣脚類(ティラノサウルス類近縁) |
| ヒプノヴェナトル | Hypnovenator matsukawaensis | 兵庫県丹波篠山市/オオヤマシモ層(ササヤマ群) | 2024 | トロオドン類(小型獣脚類) |
出典:福井県立恐竜博物館/ Dino-Tail.com/ Earth Archives/ Wikipedia英語版
この表を見ると、福井県・兵庫県・北海道の3地域が、日本における恐竜研究の中心であることがわかります。
特に福井県の「キタダニ層」は世界的にも珍しい“多種多様な恐竜が共存した地層”として注目され、
「フクイラプトル」や「フクイヴェナトル」など、複数の新属新種がここから発見されています。
各恐竜の解説
ニッポノサウルス(Nipponosaurus sachalinensis)
1936年、当時の日本領・樺太(現ロシア・サハリン)で発見された、日本で初めて記載された恐竜です。
名前の「ニッポノ(Nippono)」は日本を意味し、まさに“日本の恐竜時代”の幕開けを象徴する存在となりました。
- 発見地: 樺太(旧日本領)・ヨエゾ群
- 分類: ハドロサウルス類(カモノハシ竜)
- 記載年: 1936年(日本初の正式記載恐竜)
- 発見者: 長尾巧(地質学者)
ニッポノサウルスは全長約4〜5mの草食恐竜で、特徴的な“カモのような嘴”を持っていました。
発見当時の化石は保存状態が良く、骨格の約半分が確認されており、世界的にも希少な「若い個体」の標本として知られています。
サハリンがまだ大陸と地続きだった頃、日本列島に恐竜が生息していたことを示す歴史的証拠といえるでしょう。
ワキノサウルス(Wakinosaurus satoi)
1992年、福岡県北九州市若松区で発見された、日本国内で最初に記載された恐竜です。
名前の「ワキノ」は地名の“若松”に由来し、発見者・佐藤氏の名前も学名に刻まれています。
- 発見地: 福岡県北九州市/仙石層
- 分類: 獣脚類(肉食恐竜)
- 記載年: 1992年
見つかったのは一枚の歯――しかしその形状は、確かに肉食恐竜のものだったのです。
歯の断面は鋭く、細かいノコギリ状のギザギザ(鋸歯)があり、ティラノサウルス類に近い特徴を持っていました。
標本は断片的ながら、日本に「肉食恐竜がいた」という確かな証拠となり、後の福井発見ラッシュの“扉を開いた歯”とも呼ばれます。
現在もワキノサウルスは単独属として扱われていますが、分類学的には未解明の点も多く、将来的に「別属への再分類」や「新資料による再評価」が進む可能性があります。
フクイラプトル(Fukuiraptor kitadaniensis)
2000年、福井県勝山市のキタダニ層から発見された中型の肉食恐竜。
「福井の略奪者」を意味する名を持つ、日本を代表する恐竜のひとつです。
- 発見地: 福井県勝山市・北谷層(手取層群)
- 分類: 獣脚類(メガラプトル類に近縁)
- 記載年: 2000年
最初に見つかったのは鋭い爪の骨。その後、部分的な頭骨・前肢・後肢なども発見され、これがアジア初の「メガラプトル類」として学界に衝撃を与えました。
その姿はしなやかで俊敏。体長は約4.5m、鋭い鉤爪を武器に小型草食竜を狩っていたと考えられています。
「フクイラプトル」は日本の恐竜研究の象徴的存在であり、彼の骨格標本は福井県立恐竜博物館の中央ホールに展示されています。
この発見が、以後の福井発掘ラッシュ――「フクイサウルス」「フクイティタン」「フクイヴェナトル」など――の礎となりました。
フクイサウルス(Fukuisaurus tetoriensis)
2003年、福井県勝山市のキタダニ層から発見された草食恐竜。
日本語にすると「福井のトカゲ」。その名の通り、日本で最も有名な恐竜のひとつです。
- 発見地: 福井県勝山市・手取層群キタダニ層
- 分類: 鳥脚類(イグアノドン科に近縁)
- 記載年: 2003年
体長は約4.7m。頭部がやや平たく、前歯の構造から植物をすり潰すのに適した歯列を持っていたと考えられています。
前脚を地面につけて歩く「四足歩行型」の草食恐竜で、群れで生活していた可能性もあります。
この恐竜の発見は、同じ福井産の肉食恐竜「フクイラプトル」と対をなすもので、1億2000万年前の北陸に“捕食者と被食者の関係”が存在していたことを示す重要な証拠となりました。
アルバロフォサウルス(Albalophosaurus yamaguchiorum)
2009年、石川県白山市のクワジマ層から発見された、小型の草食恐竜です。
名前の「アルバロフォ」は“白い稜(ridge)”を意味し、頭部に特徴的な突起を持っていたことから名づけられました。
- 発見地: 石川県白山市・手取層群クワジマ層
- 分類: 鳥盤類(マルギノケファリア類に近縁)
- 記載年: 2009年
頭骨の一部しか見つかっていませんが、骨の構造から「角竜(トリケラトプス類)」や「パキケファロサウルス類」と近い系統の初期型と考えられています。
日本では珍しい“頭飾りを持つタイプの草食恐竜”であり、当時の北陸が乾燥した大地と森の混在した環境だったことを示唆しています。
学名の種小名「yamaguchiorum」は、化石を寄贈した山口家への献名。
発掘に関わった人々の想いが、学名に刻まれた美しい例でもあります。
フクイティタン(Fukuititan nipponensis)
2010年、福井県勝山市のキタダニ層から発見された、日本最大級の恐竜です。
名前の「ティタン(Titan)」は“巨神”を意味し、その名にふさわしい堂々たる姿をしていました。
- 発見地: 福井県勝山市・手取層群キタダニ層
- 分類: 竜脚類(ティタノサウルス形類)
- 記載年: 2010年
推定全長は約10m以上。長い首と尾を持ち、巨体ながらも優雅な姿をしていたと考えられています。
体重は約13トン、ゆったりとした四足歩行で森林や湿地を移動し、シダ植物を食べていたのでしょう。
フクイティタンの骨格は、複数個体の化石が同じ地層から出土しており、これは群れで暮らす竜脚類の社会性を示唆するものといわれています。
「日本にも巨大竜がいた」――その事実は、世界の恐竜地図を書き換える発見でした。
タンバティタニス(Tambatitanis amicitiae)
2014年、兵庫県丹波市の佐曽利層(ササヤマ群)から発見された巨大な草食恐竜。
名前の「タンバティタニス」は「丹波の巨神」を意味します。
- 発見地: 兵庫県丹波市/佐曽利層(ササヤマ群)
- 分類: 竜脚類(ティタノサウルス形類)
- 記載年: 2014年
発見されたのは尾椎や肋骨など約160点におよぶ骨の化石。
それらを組み合わせた結果、全長約15mに達する巨大な体を持っていたことが分かりました。
当時の西日本は温暖湿潤な気候で、タンバティタニスはその広大な低地をゆったりと歩いていたのでしょう。
学名の種小名 amicitiae(アミキティアエ)は「友情」を意味し、地元住民と研究者の協力による発見であったことを称えて名づけられました。
科学と地域の絆が生んだ、日本らしい一体です。
コウシサウルス(Koshisaurus katsuyama)
2015年、福井県勝山市のキタダニ層から発見された、小型の草食恐竜。
「コウシ」は福井県勝山市の地名“越(コウシ)”に由来します。
- 発見地: 福井県勝山市/手取層群キタダニ層
- 分類: 鳥脚類(小型草食)
- 記載年: 2015年
全長約2mほどの小型恐竜で、素早く動ける軽量な体構造を持っていました。
下顎の歯列構造はイグアノドン類に似ており、「フクイサウルス」との進化的つながりを示す中間的な特徴を備えています。
この恐竜の発見は、日本の鳥脚類の多様化を示す重要な証拠とされています。
同じキタダニ層で複数の草食恐竜が共存していたことから、
当時の福井が“豊かな植生と競争のある環境”だったことがうかがえます。
フクイヴェナトル(Fukuivenator paradoxus)
2016年、福井県勝山市のキタダニ層から発見された、鳥に近い小型獣脚類。
名前の「ヴェナトル(Venator)」は“狩人”を意味し、その俊敏な動きを表しています。
- 発見地: 福井県勝山市/手取層群キタダニ層
- 分類: 獣脚類(マニラプトル類に近縁)
- 記載年: 2016年
フクイヴェナトルは、ほぼ完全な骨格が得られた日本初の獣脚類恐竜です。
その体は全長2.5mほど、体重は約25kg。歯の形や骨格構造は非常に“異例(paradoxus)”で、肉食・雑食・鳥類的特徴をあわせ持つ、まさに“進化の交差点”に立つ恐竜でした。
特に頸椎の構造は鳥類に酷似しており、「恐竜から鳥へ」という進化の流れを解く上で欠かせない資料とされています。
この発見により、福井の地が“進化研究の聖地”として世界から注目されることになりました。
カムイサウルス(Kamuysaurus japonicus)
2019年、北海道むかわ町で発見された日本最大級の恐竜。
その名はアイヌ語の「カムイ(神)」に由来し、まさに“神の竜”として知られています。
- 発見地: 北海道むかわ町/ヨエゾ群ハコブチ層
- 分類: ハドロサウルス類(カモノハシ竜)
- 記載年: 2019年
発見された骨格は全長8m以上に及び、日本で最も完全な恐竜化石といわれています。
2003年に地元の高校生が偶然見つけた一片の骨から始まった物語は、16年の歳月を経て、ついに「新属新種」として世界に認められました。
カムイサウルスは海辺に生息していたハドロサウルス類で、潮の満ち引きに合わせて移動していたと考えられています。
この恐竜の発見は、「恐竜は内陸の生物」という常識を覆すものであり、日本がかつて“恐竜が海辺を歩いた国”であったことを示す貴重な証拠です。
ヤマトサウルス(Yamatosaurus izanagii)
2021年、兵庫県淡路島で発見された草食恐竜。
名前の「ヤマト」は“日本”を象徴し、「イザナギ」は日本神話の創造神に由来します。
- 発見地: 兵庫県南あわじ市/キタアマ層
- 分類: ハドロサウルス類(原始的カモノハシ竜)
- 記載年: 2021年
発見されたのは顎の骨を中心とした部分化石ですが、歯の構造が非常に独特で、北米とアジアのハドロサウルス類の“進化の分岐点”を示す証拠とされています。
体長は約7m。カムイサウルスよりも原始的な特徴を持ち、日本列島が“恐竜の渡り道”だった可能性を物語る存在です。
発見地の淡路島は、恐竜時代には大陸と地続きの沿岸部でした。
つまりヤマトサウルスは、太古の“瀬戸内海の岸辺”を歩いていた恐竜なのです。
パラリテリジノサウルス(Paralitherizinosaurus japonicus)
2022年、北海道三笠市のオソウシナイ層から発見された新種。
その名の「パラリ(Parali)」は“海の近く”を意味し、海辺に暮らした珍しい恐竜として知られています。
- 発見地: 北海道三笠市/オソウシナイ層(ヨエゾ群)
- 分類: テリジノサウルス類(長腕を持つ草食獣脚類)
- 記載年: 2022年
発見されたのは巨大な前肢の爪の骨。
湾曲したその爪は長さ約25cmに及び、日本で見つかった中で最大級の肉食系形状でした。
しかし実際には草食または雑食で、長い腕を使って植物をかき寄せていたと考えられています。
パラリテリジノサウルスの発見は、「海辺に適応したテリジノサウルス類」という全く新しい進化の可能性を示しました。
つまり、日本の恐竜は単なる“陸の巨竜”ではなく、多様な環境に生きた“適応の名手”だったのです。
ティラノミムス(Tyrannomimus fukuiensis)
2023年、福井県勝山市のキタダニ層から発見された最新の新属新種。
その名の「ティラノミムス」は、“ティラノサウルスに似た者(模倣者)”を意味します。
- 発見地: 福井県勝山市/手取層群キタダニ層
- 分類: 獣脚類(ティラノサウルス類近縁・オルニトミモサウルス類)
- 記載年: 2023年
発見された骨格は首から尾までを含む部分的な全身化石で、保存状態は極めて良好。
細長い後肢と軽量な骨格を持ち、肉食というよりは雑食性で俊敏な走行恐竜だったと考えられています。
「ティラノサウルスの祖先的特徴を残す種」として、世界的にも大きな注目を集めました。
特筆すべきは、福井県がこれで6種目の新属新種を誇る地域となったこと。
この発見により、キタダニ層が“アジア最大級の多様性を持つ恐竜化石地”であることが改めて証明されました。
ヒプノヴェナトル(Hypnovenator matsukawaensis)
2024年、兵庫県丹波篠山市のオオヤマシモ層(ササヤマ群)から発見された、
日本で最も新しい新属新種の恐竜です。 名前の「ヒプノ(Hypno)」は“眠る”、「ヴェナトル(Venator)」は“狩人”を意味し、
「眠る狩人」という幻想的な名前が与えられました。
- 発見地: 兵庫県丹波篠山市/オオヤマシモ層(ササヤマ群)
- 分類: トロオドン類(小型獣脚類/鳥類に近縁)
- 記載年: 2024年
体長はおよそ1.5〜2mほど。脳の構造から高い知能と視覚能力を持っていたと考えられています。
このグループは鳥類の直系に近く、ヒプノヴェナトルの発見は「日本にも鳥の祖先が生息していた」ことを示す画期的な成果です。
研究者たちは、化石が発見された地層の環境から、ヒプノヴェナトルが夜行性だった可能性を指摘しています。
“夜の森を駆ける狩人”――その姿は、まさに名前の通り「眠る森の捕食者」だったのかもしれません。
地方別に見る“恐竜王国ニッポン”の発見地マップ
恐竜化石の発見地を地図で眺めると、ある特徴が見えてきます。
それは、日本海側から西日本にかけての地層に集中しているということ。
かつて大陸と地続きだった頃の日本は、恐竜たちにとって“アジアの縁辺”―― つまり、新しい進化の実験場だったのです。


-恐竜図鑑-2-300x164.jpg)