プシッタコサウルスは、白亜紀のモンゴル、中国に生息していた草食恐竜です。ここではプシッタコサウルスの基本的な情報から特徴、発見された場所と化石、分類、名前の由来などをご紹介します。
目次
プシッタコサウルスの基本情報
| 属名 | Psittacosaurus |
| 種名(種小名) | Psittacosaurus mongoliensis |
| 分類 | 鳥盤類 > 角竜下目 > プシッタコサウルス科 |
| 生息時代 | 白亜紀前期(約1億3,000万 – 9,960万年前) |
| 体長(推定) | 約1~2メートル |
| 体重(推定) | 約20キログラム |
| 生息地 | モンゴル、中国、タイ、ロシア |
| 食性 | 草食 |
プシッタコサウルスの大きさイメージ

プシッタコサウルスの概要

プシッタコサウルスの特徴
プシッタコサウルスは、白亜紀前期にアジアで生息していた小型の草食恐竜です。全長はおよそ2メートル、体重は20キログラムで、成体は主に二足歩行をしていたと考えられています。特徴的なのは、オウムのくちばしに似た硬い嘴で、これにより硬い植物や種子も食べられたとされています。また、体表の大部分は鱗で覆われ、尾の上部には剛毛状の構造が一列に並んでいた化石も発見されています。この剛毛が羽毛由来なのか、特殊な鱗なのかは議論が続いています。さらに、前肢の指が4本しかないことや、角やフリルを持たない点、眼の前にある「前眼窩窓」が消失している点も特徴的で、後に進化した角竜類とは異なる原始的な特徴を多く残していました。
プシッタコサウルスが発見された場所と化石
プシッタコサウルスの化石は非鳥類型恐竜の中で最も種の豊富な属であることで有名です。
1923年、モンゴルでアメリカ自然史博物館の探検隊によって初めてプシッタコサウルスの化石が発見されました。その後、中国、モンゴル、ロシア、タイなどアジア各地で化石が見つかっています。特に中国北部やモンゴルからは数百点にも及ぶ標本が報告され、その中には完全な骨格も多く含まれています。
あわせて読みたい
恐竜の化石が多い国ランキングTOP10|世界の恐竜大国と代表種まとめ
恐竜の化石は世界各地で発見されていますが、国によってその種類や発見数には大きな差があります。中には何百種類もの恐竜化石が見つかっている「恐竜大国」もあれば、…
化石が見つかる地層の年代は、およそ1億3,000万〜1億500万年前で、当時の環境や動植物の生態系を知る手がかりにもなっています。化石の中には、幼体が集団で保存されているものや、捕食者との格闘の痕跡が残るものも、さらには、保存状態の良い外皮や色素が残る標本も含まれています。これらは当時の生態や行動、外見を推測するうえで重要な資料となっています。
発見場所:モンゴル ドルノゴビ県
大きさ-恐竜図鑑.png)
-恐竜図鑑-4.jpg)

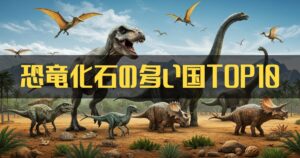

-恐竜図鑑.jpg)
-恐竜図鑑-1-300x164.webp)

|原始的な肉食恐竜の誕生【恐竜図鑑】-1-300x164.webp)
|幻のカモノハシ恐竜の謎【恐竜図鑑】-1-300x164.webp)
|謎に包まれた日本の古竜【恐竜図鑑】-2-300x164.webp)
-恐竜図鑑1-300x158.jpg)
-恐竜図鑑-300x158.jpg)
-恐竜図鑑-300x164.jpg)